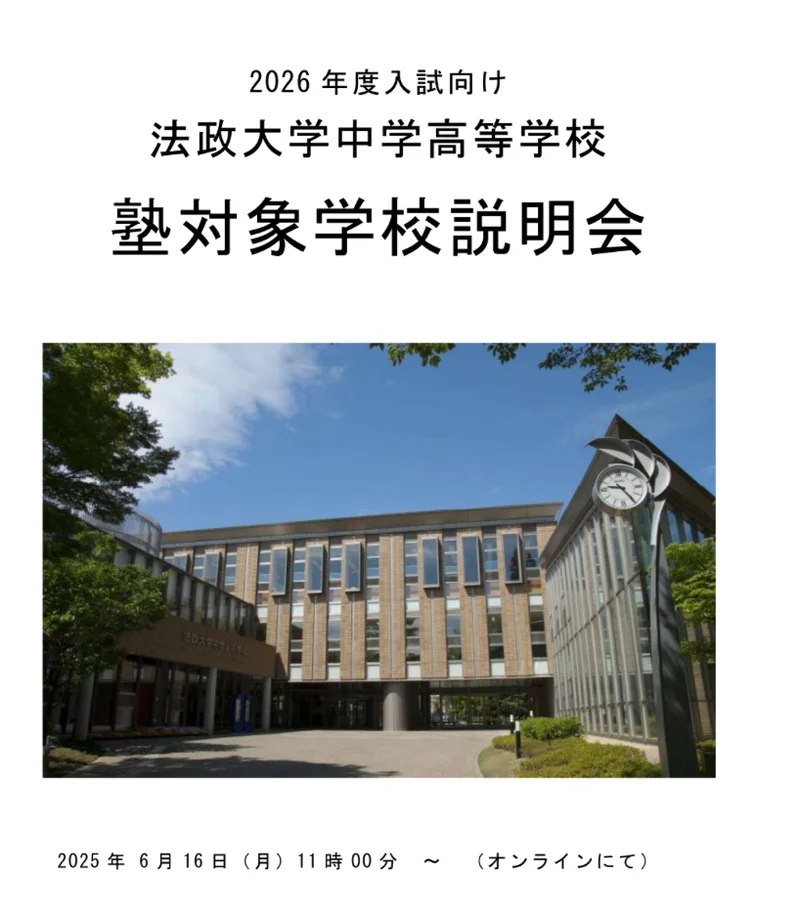学校図鑑
2025.05.13
令和7年5月13日 日本大学第二中学校・高等学校 塾関係者対象説明会
令和7年5月13日は東京都杉並区にある日本大学第二中学校の塾対象説明会に2名で参加してきました。
現在ジャングルジムからは3期生と5期生が通っています。

今回の説明会は高校校長・広報室長の中島先生が最初から最後までしてくださりました。
色々な学校の説明会に参加しておりますが、校長先生の挨拶は短時間で、各セクションごとに先生が変わってお話しするという形式が多数派で今回のように1時間30分校長先生自らお話しされるということは珍しいのかなと思います。
学校の顔として校長自ら全部の説明をするというところに心から敬意を表したい気持ちになりました。
さて、日大第二についてですが、多くの方は「日本大学の付属校」として同校のことを把握されているのかと思います。
もちろん都内に8校(うち中学受験で入れる学校は6校)、全国26校の日本大学の付属校であることは間違いないのですが、日本大学の法人としては日本大学とは別であり、日本大学に進学する割合は卒業生の35.4%(2024年度卒業生)ということで、他の日大系の学校とは一味違う、そんな学校といえそうです。
進学結果につきましては後で述べますが、日大第二の校風は「おおらかで明るい」ということで、特進クラスやスポーツクラス・スポーツ推薦を設けず、多様な価値観を養い温かみと思いやりあふれる人間へと成長すること、社会人基礎力の養成を目指した教育を行なっております。
具体的には先取り学習を行わず、公立中学校と学習進度は同じだが、授業時間が公立と比べて多いことからその分を深掘りしていく、振り返り学習に重点を置いています。
中学での学習に苦戦してしまっている生徒へのフォロー、底上げについて説明会でも詳しく説明されていましたが、逆にどんどん進んでいきたい、難関大学を目指しているという層に対しても、上級生向けの講習(英検の上の級の対策や数学の先取り)に下級生が参加できるような仕組みも整えており、急がず焦らずのカリキュラムがしっかりと活きるような学習環境なのではないかと思いました。
よく、中高一貫校に進学するメリットとして、中3で足踏みをせずに先取り学習を行えるので高3の1年間を受験対策に充てることができ、それが大学進学に有利に働きますよ ということが挙げられ、私どもも中学受験をするメリットのひとつとして上記のようなことを述べたりするのですが、このような中高一貫校もあるということと、それによってどのような効果があるのかというところについて日大第二の取り組みにも大きな魅力があるものと思っております。
部活動もさかんで14の運動部と18の文化部があり、部活加入率は80%以上ということで、近年公立中学校が教員の労働環境などの面から部活動を学校の外に出そうという動きがある中で、中島校長ははっきりと「私学なのだから部活動の中にしっかりと生徒の居場所を作ってあげることが大切だ」とおっしゃっており、個人的に部活を重視する派の早川は嬉しい気持ちになりました。
昨年では高校野球部が後2回勝てば甲子園というところまで、勝ち進んでいました。
私も夏期講習の合間を縫って、日大第二と早稲田実業の準決勝を見ていたのですが(準々決勝の國學院久我山と早稲田実業の試合ではジャングルジム2期生が4番で出場し先制の3ランホームランを放ったのですが惜しくも敗れてしまいました)、打席に入る際に中継のテロップに入る日大第二の選手たちの出身中学校が日大第二中となっていたことが多く、スポーツ推薦を行なっていない学校でも、しっかりと強豪校に渡り合っていて素晴らしいなと思いました。
中学で部活動に入って頑張っていても高校からたくさんスポーツ推薦で入ってきた子がレギュラーメンバーを独占してしまい、ほとんどの中入生が高校で試合に出ることができないということが多いのですが、日大第二ではこのようなことは制度の面ではなさそうなので、スポーツ男子・女子にはピッタリなのではと思いました。
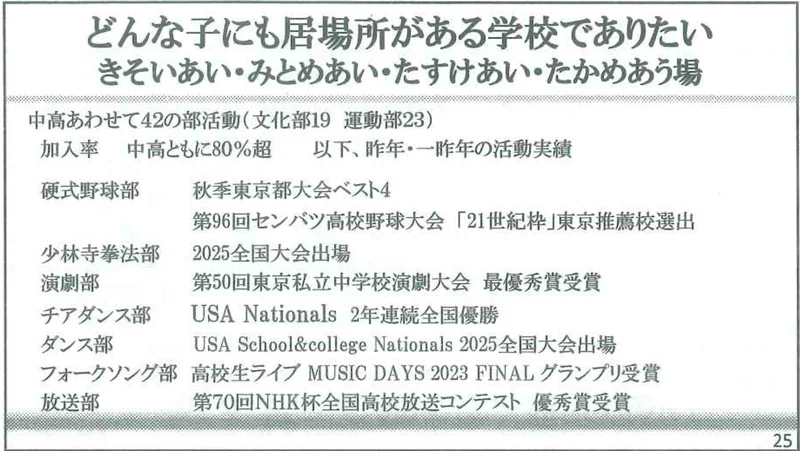
さて、大学進学状況についてですが、先述した通り日本大学に進学する割合は卒業生の35.4%(2024年度卒業生)となっており、他の日大付属と比較しても、指定校推薦を使用する割合が高く、卒業生のうち約60%がいわゆる年内入試(指定校推薦、日大推薦、公募)で大学を決めています。
指定校推薦についてですが枠として
早稲田→4名、上智→5名、成蹊→9名、中央→7名、学習院→6名、立教→6名、明治→6名、東京薬科→1名、日本女子→1名、
東京女子→3名、法政→4名、東京理科→11名、成城→5名、武蔵→3名、青山学院→5名、同志社→1名
で合計すると81名分あります。
そこに、学校推薦型・総合型・一般受験を加えて卒業生の51.7%が日大以外の大学に進学、進学準備は12.0%とのことでした。
また、全国26校の日大付属校で日大医学部の推薦枠は15あるのですがこのうち3名が日大第二であるということを考えると、学力的に引っ張っている学校と言うことができるのかと思います。
日大ありきでない方をお預かりする
ということを校長先生もおっしゃっていましたので、大学付属校としての学校選びにこのような多彩な進路ということも加えて同校を検討してみるべきなのかなと思います。
国際理解教育(留学プログラムなど)についてもコロナ禍による移動の制約がなくなったことで各校で再開していることかと思いますが、日大第二では創立100周年に向けて見直しをしていくとのことで、ずっと行なっているアメリカ・イギリスに加えてオーストラリアが加わったり、台湾や東南アジアの国々を検討したりという段階にあるそうです。
また、円安により負担額が大きくなってしまっているということにも注目し、方面と費用にバリエーションをもたせるようにしていく方針です。
最後に入試についてです。
現高3が中学受験をしていた2019年の同校の偏差値(80%四谷大塚)が
男子1回 43
女子1回 43
男子2回 43
女子2回 43
で今年が
男子1回 44
女子1回 44
男子2回 45
女子2回 45
となっております。
目黒日大や日大豊山などが人気となっていることから、日大付属中の中で受験生の取り合いとなっている状況なのかとは思いますが、日大第二の併願校としては男子が東京電機大学や成蹊、女子が明治学院や大妻中野が多くなっているとのことです。
ジャングルジムではGMARCH付属校と同校を併願するということがあるのですが、
2月1日 明大八王子① 法政大学① 中大附属① 日大第二①
2月2日 学習院① 明大中野① 明大明治①
2月3日 学習院② 明大八王子② 法政大学② 日大第二②
2月4日 明大中野② 中大附属②
※全てのGMARCH付属校ではありません
というような受験日程で、比較的MARCHの中でも合格しやすい学校いえる明大八王子や法政大学と日大第二が完全に日程が被ってしまっているということがあり、比較的高い学校(特に女子は学習院と明大中野を受けられないので)しかない2日に明治学院などを受けるということが多くなっているかと思います。
例えば、法政大学が第一志望ということとなると
1法政大学 2明治学院 3法政大学 4明治学院or成蹊or中大附属 5法政大学
という併願が一般的で、そこに日大第二を入れると純粋に1回分チャレンジができないということとなってしまいます。
これは第一志望が明大八王子の場合でも同じです。
では、第一志望が明大明治や青山学院といった2月2日の受験校ということとなると、1日の受験校は中大附属、法政大学、明大八王子、成蹊、もしくは早稲田実業や立教女学院となってくることが多くなってくるものと思われます。
ではでは、第一志望が学習院ということであれば、1日に日大第二を受けて2日、3日に学習院と受けていけそうですが、ここで1日の日大第二に不合格となってしまうと3日の学習院②の受験(算数などが①の問題を復習することで解ける問題が多くなるお得な回)が日大第二とバッティングしてしまうこととなります。
中島先生も今後は午後入試や2科入試を新設してなるべく受けやすいようにということは検討していくこととなるかもしれないとお話しされていましたが、それによってどのように大学付属校の併願パターンが変わっていくか、また、今年から明治大学世田谷がこれらの候補に加わった際(所沢地域からは少し受けにくいですが)どのような変化が考えられるのか注意深く見ていこうと思っています。