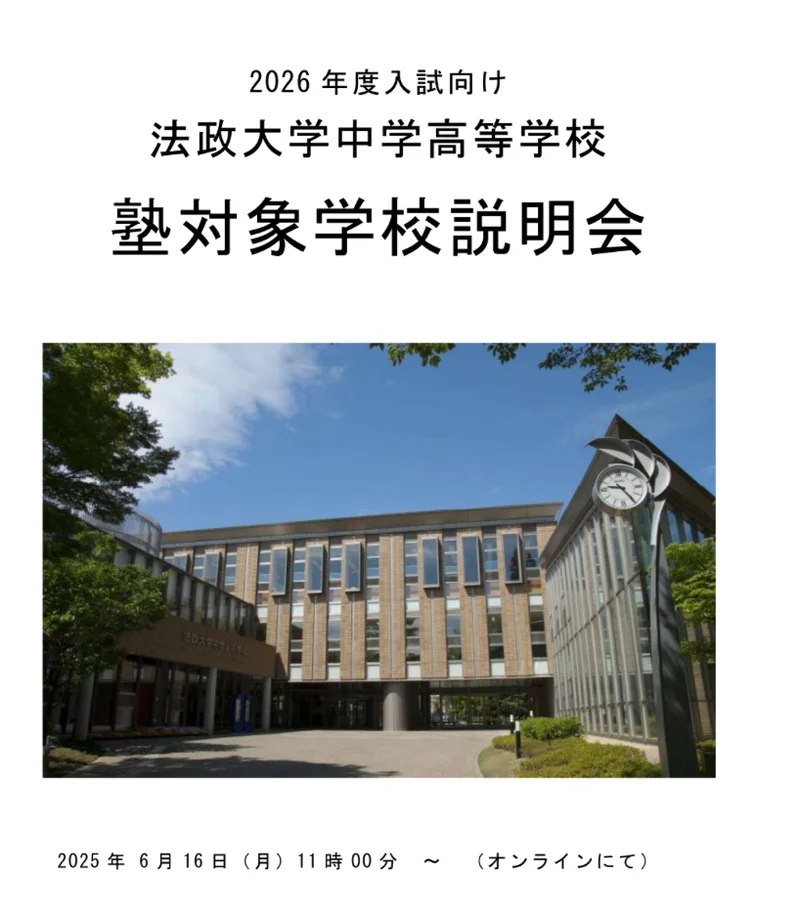学校図鑑
2025.05.26
令和7年5月26日 桐朋中学校 塾関係者対象学校説明会
令和7年5月26日本日は、東京都国立市にあります桐朋中学校の教育関係者対象学校説明会参加してまいりました。

ジャングルジムからは現在4期生と7期生が通っております。

まずはじめに学校長の原口先生より「桐朋教育の目指すもの」というテーマでお話がありました。
自律的な学習者の育成という方針のもと、一人ひとりが、試行錯誤しながら学習の方法や方略を見つけ、自ら学んでいくために学校側が様々なきっかけを生徒に与えていくことで、自律的な学びを促すスイッチとなるようにというお話は毎回の説明会で語られているところとなりますが、どの話も毎回同じでなく、教員の専門性を活かし、希望者を対象に放課後に実施される特別講座はどれもがとても充実した内容になっているのだろうなと思うことができます。
これは桐朋独自の研修制度を活用し、教員が大学院で研究した成果を生徒に還元しているということが、毎年同じようにならない理由であり、教員が探究心を持って学問を楽しむ姿が生徒たちが学問への関心を高め、学ぶ喜びを知る機会になっているというところが本校の特徴なのではないかと思います。
次に入学試験からの学びというテーマでお話がありました。
各科目の先生が入れ替わりで説明してくださるという形が一般的なのですが、桐朋では入試広報部長の先生が4科目全て行います。
先生のご担当は国語とのことですが、どの科目も伝聞形式のものではなく、先生が解いた実感なども込められて語られており、先述した探究心を持って学問を楽しむ姿というこの学校の雰囲気というものを感じました。
国語については
本文を自分のこととして、あるいは自分につながることとして主体的に受け止め、その内容を適切に把握するとともにしっかりと考え自分のことばで整理することができる児童を待っています
という方針で入試問題を作成しており、部分と全体を行ったり来たりできるような力を見る問題を出題しております。
また、本文の趣旨から離れ、道徳的に正しいと考えられる一般論を答えてしまうような誤答が散見される問題というものも今年はあり、塾で習うテクニックのようなところが通用しにくい問題というものがあるのかなと感じます。
この入試を突破して入学した桐朋生たちは平常授業において班発表や中2の文法作文、中3の小論文やコラムの執筆など、自分の言葉で整理する機会というものが多く、こちらがいわゆる【バスった】卒業生代表の答辞なのですが、このような心が動かされるような文章が書けるようになるのも同校の日々というものがあるのではないかと思います。
算数については
自ら考え、試行錯誤を行い、失敗を恐れず挑戦するという力を試すものとなっていて、
いわゆる典型問題だけでなく、初めて見るであろう設定の問題を小問を通じて様々試行錯誤できるような工夫をして作問しているとのことです。
この入試を突破して入学した桐朋生たちは、平常授業で宿題を生徒に板書してもらい、それを添削しながら様々な解法や表現を学び、それは高校の演習授業でも問題を板書してもらうスタイルが続き、「模範解答」からは得られない味わいがあります。
したがって、解法暗記的な勉強法でなく、普段から同じ問題を色々な角度から注意深く観察し多くを吸収する学びをしてほしいという思いを込めて作問されています。
理科については
基本知識と身近な科学に関する考察問題を出題することで、自然科学に関する興味や素養を確認し、記述問題やグラフ問題等で正しく表現する力を確認することをねらいとしています。
入学後の授業については、実際に体験してみることで頭の中だけでイメージできないことに新たな発見が得られように、また、その体験を授業で学ぶ内容につないでいけるような指導を心がけているとのことです。
知識を入れるだけでなく、未知の話題でも問題の文章やデータに合わせて、その場で理解、思考できるようにしてもらいたいとのことです。
社会については
教科書を中心とした基本的内容に加えて、「知的関心」を喚起できるような問題を例年出題しています。論述問題も基本的には例年出題されています。
一部正答率の低い問題もありますが、平均点は概ね高く、最後の配点の高い論述問題の対策を厳に行っていければあとは特別な対策は存在しないだろうと私は思っています。
入学後の授業については、社会科見学を中1、中2で行い、中3の修学旅行にもこの要素が含まれます。
実際に訪れて学ぶことで教科書上の知識が自分自身と関わりのあることだと感じることが出来ているとのことです。
説明会の帰りが毎年中間試験後の桐朋生と同じになるので、国立駅までしばらく一緒に歩いていく形となります。
桐朋生たちの話が必然的に耳に入ってくるのですが、今日は「独立戦争について3行しか書けなかった〜」というものがありました。
きっと、知識をつめていくということではなくしっかりと筋道を立てて自分の言葉で説明する問題というものが定期テストでも出題されているのだな。と思いました。
入試全体の話としては2026年度入試は2025年度入試と大きな変更点はない予定とのことです。
最後に、進路指導についてのお話がありました。
合格実績などの話はサラッとしているところについて、先生は「卒業生たちの進路はひとりひとりの顔が思い浮かんで、数字ではピンとこない」とおっしゃっていたことが印象的でした。
2025年度は合格体験率は75%、現役進学率は58%となっています。
学校のホームページに詳しく掲載されていますので、詳細はご覧ください。
先日説明会に参加した本郷高等学校が東大15名(うち14名が現役)で、桐朋高等学校が東大14名(うち現役11名)となっています。
日頃の授業では、大学受験を無視していないが意識もしていないがその分夏期講習では受験に特化した内容を行うことでサポートしていく体制であるというところと、今年は例年に比べてやや理系の生徒が少なかったが「男の子なんだから理系に行けよ」というようなことが言わないということで、生徒の自主性を尊重しています。
そして、OBの協力が大きい学校という同校の特徴から社会で活躍する先輩たちの姿というところが在校生の刺激となっているとのことです。
また、年内で進路を決めるという時代の流れについては、今のところ入試は年明けという状況は動かないだろう、ただし使えるものは使っていくという方針だそうです。
今年度は指定校推薦により進学者は8大学11学部に12名が進学しました。
その内訳は
学習院大学(文)
慶應義塾大学(商)
慶應義塾大学(商)
慶應義塾大学(理工)
国際基督教大学(教養)
中央大学(法)
東京理科大学(工)
武蔵野美術大学(造形構想)
立命館アジア太平洋大学(アジア太平洋)
早稲田大学(先進理工)
早稲田大学(創造理工)
早稲田大学(文化構想)
となっています。
桐朋高等学校の今年の卒業生に、オークランド・アスレチックスに入団し、MLBに挑戦した選手がいます。